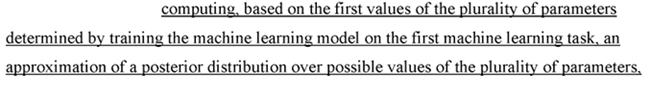
|
Ex Parte Guillaume Desjardins et al. Squires新長官らによるARP審決 Decision by JOHN A. SQUIRES (New Director of
USPTO), WALLACE (Acting Commissioner for Patents, and KIM (Vice Chief PTAB
Judge) |
本件は、先日USPTOの長官に就任したJohn Squires氏(+2名)による上訴審判パネル(Appeals Review Panel: APR)による審決に対するレビュ結果(APR審決)である。そもそもクレームは審査において自明であるとし拒絶されたが、2025年3月、審判部において101条の適格性を満たさないという新たな理由でも拒絶された。新長官Squires氏(+2名)によって審決の101条の拒絶が破棄された。
ARPは、当該発明が「第1の学習タスクで得た知識を保持しながら、第2のタスクを学習する」という継続学習(continual learning)に技術的改善をもたらすものであり、単なる数学的アルゴリズムにとどまらず、機械学習モデル自体の機能的向上を実現する「技術的改良」に該当すると判断した。またARPは、審判部が職権で101条拒絶をしたことを批判し、Enfish事件(CAFC: 2016年)などの確立された判例に基づく分析を怠った点を問題視した上で、今後はAI関連発明を一律に「抽象的アイデア」として排除すべきではないとの見解を示した。
さらにARPは、「102条、103条および112条こそが特許保護の範囲を適正に決めるための伝統的かつ適切な手段であり、審査の焦点はこれらの条項に置くべきである」と指摘し、AI技術分野における101条の過度な適用を戒める方針を明確に示した。
このARP審決は司法判断ではないが、USPTO内部の最終的判断として、今後のAI関連発明に対する審査官および審判官の101条判断に強い影響を及ぼす指針的決定と位置づけられるだろう。
Squires長官の特許適格性に対する考え方は、2019年に101条審査ガイダンスを策定したIancu長官の方針と非常に近い。すなわち、発明が特許となるか否かは、102条(新規性)、103条(進歩性)、および、112条(記載要件・明確性・実施可能要件)の審査によって十分に判断できるものであり、101条はこれら三つの法定要件を補うための規定ではないという立場である。
将来的には、101条の改正法案が成立し、Mayo/Alice最高裁判決による法理が全面的に否定され、2012年以前のより明確で予測可能な101条判断基準に回帰する日が訪れると考えられる。(以上筆者)
***********************************************
■ 特許出願人:Google LLC
■ 関連特許:US Patent Application No. 16/319,040 (以下特許)
出願日:2017年7月18日(2016年7月18日の仮出願から)
■ 特許発明の概要:
一言でいうと、本件出願の発明は人工知能(AI)や機械学習の「忘れる問題」を防ぐ技術で、人間に例えると、「新しいことを学ぶと、前に覚えたことを忘れてしまう」──この現象をAIでも同じように起きる「忘却(catastrophic forgetting)」。
対応する明細書の開示(要部のみ)
いくつかの機械学習モデルは、受け取られた入力に関する出力を生成するためにモデルの複数の層を使用する深層モデル(deep model)である。たとえば、深層ニューラルネットワークは、出力を生成するために、受け取られた入力に非線形変換をそれぞれ適用する出力層および1つまたは複数の隠れ層を含む深層機械学習モデルである。しかし、機械学習モデルは、複数のタスクに関してトレーニングされる場合に「破滅的忘却(catastrophic forgetting)」を被り、新しいタスクが学習されるときに前のタスクの知識を失う場合がある・・・
■ 代表的なクレーム1(要部のみ):
複数のパラメータを有する機械学習モデルをトレーニングするコンピュータ実装方法であって、
・・・(略す)・・・
前記機械学習モデルが前記第1の機械学習タスクに関して許容可能なレベルの性能を維持しながら第2の機械学習タスクに関して許容可能なレベルの性能を達成するように、前記第1のパラメータ値を調整するために前記トレーニングデータに関して前記機械学習モデルをトレーニングすることによって前記第2の機械学習タスクに関して前記機械学習モデルをトレーニングする・・・
この部分は、「AIが古い知識を保ったまま新しい知識を学ぶ」ための仕組みを規定している。つまり、「前のタスクでの性能を維持しながら、次のタスクでもうまく動くように、慎重にモデルを再調整する」という手順を定義している。
■ 審査官の判断:
最終的にクレーム1-6, 8-20を自明であると判断した。クレーム7は出願人がキャンセル。
■ 審判部の判断(審決)(2025年3月4日):
上記審査官の拒絶理由(自明性)は概ね支持された。審判部は新たにクレーム1-6及び17-20を特許適格性違反(101条)で拒絶した。2019年の101条審査ガイダンス(改訂版:Prong OneとProng Two)基づき101条で要求される適格性が無いという理由で拒絶した。
■ 新長官+2名(上訴審判パネル)によるレビュ:(2025年9月26日)
審決の新規101条拒絶を破棄し、審判部に差し戻す。
以下の手順、USPTOのSTEP2A(Prong
ONEとProng TWO)、に基づきクレームの特許適格性を判断する。
|
「MAYO/ALICE」 最高裁による判断基準 |
USPTO MPEP 2106.04 & 2106.05 |
|
Whether claim is “directed to” a Judicial Exception? |
USPTOのSTEP2A (Prong ONE):
クレームにJE(司法による例外)が規定(recites)されているか? JEとは[i] 自然法則; [ii] 自然現象; [iii] 抽象的なアイデア(Abstract Idea); 尚、Abstract Ideaは以下の3つのカテゴリーに分類: [i] 数学の概念; |
| USPTOのSTEP2A (Prong TWO)
上でYESの場合には、クレームがJEを統合し実用的に応用しているかを判断する。 [Ask whether claim integrates the judicial exception into a practical application?] JEを実用的に応用している場合にはクレームはJEに”directed to”していないと判断し、101条のEligibilityを満たす。 |
|
|
ALICE Step 2 それ以外のステップにおいてクレームが全体として特許不可主題をはるかに超えたものに変換されていることが要件(Claim as a whole “significantly more than” Judicial Exception??) |
USPTOのSTEP2B
(略す) |
上記Tableに基づき101条の適格性を判断する。
Alice Step 1(USPTOのStep 2A、Prong ONE)
審判部が、クレーム1(及び他の独立クレーム18と19)の以下の構成要素が抽象的な概念(Abstract Idea:即ちJE「司法上の例外」)であると判断し、クレーム1、18,19がAbstract Ideaを規定していると判断したことには同意できる。
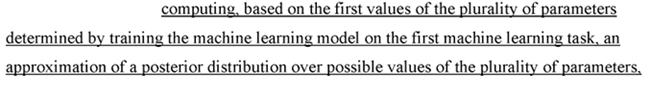
Alice Step 1(USPTOのStep 2A、Prong TWO)
審判部はクレーム1、18、19において上記したJE(司法上の例外)以外の構成要素、或いは、JEと組み合わせたとしてもJEを統合し現実的な適用はないと判断した。審判請求人はクレームの他の構成要素はコンピュータの機能を向上、或いは、同技術分野に改良をもたらすと主張した。すなわち、本願発明は、継続学習およびモデル効率における課題に対処することで、記憶(ストレージ)容量を減らし、連続的なトレーニングにおいてタスク性能を維持することにより、従来のシステムに対して技術的改良を提供する」と主張している。その裏付けとして、明細書の段落[0021]を引用している(同7〜9ページ参照)。また8ページでは、「このトレーニング手法により、モデルは新しいタスクを学習しても以前のタスクにおける性能を維持することができ、継続学習システムにおける『破滅的忘却(catastrophic forgetting)』という技術的問題に直接的に対処している」とも述べている。
我々(新長官+2名)は、この点について審判請求人の主張に同意する。この判断を行うにあたって、「発明に対する追加要素の重要性を評価する」必要があり、その際「究極の問題」は「例外(抽象的アイデアなど)が実用的な応用に統合されているかどうか(“whether the exception is integrated into a practical application”)」であることに留意すべきである(MPEP §2106.04(d)(II)参照)。
一般的に、JE(司法上の例外)を特定の技術分野に関連づけるだけでは適格性を満たさない。しかし、クレームがコンピュータの機能を向上する、或いは、技術分野に向上をもたらす場合には同クレームは適格性を備える。
Enfish判決は、クレームが技術分野に改良をもたらしたことで適格性を認めたCAFCの初期の判例の一つである。Enfishで判示されたようにコンピュータ関連技術における改良とはソフトウェアの改良であり、物理的な特徴によるものではなく、寧ろ、論理構造且つそのプロセスに発現するのである。ソフトウェアはコンピュータ技術において非抽象的(現実的)な改善をもたらすことが可能である。
本件では審判請求人が主張するように、機械学習モデルをトレーニングすることに改善をもたらすのである。そのような明細書の記載のみでは不十分であるが、クレームの構成要素がそれを反映している。クレームの以下の箇所が本件発明における改良に貢献していると理解する。
"adjust the first values of the plurality of parameters to optimize performance of the machine learning model on the second machine learning task while protecting performance of the machine learning model on the first machine learning task."
101条適格性の判断基準が混乱している現況に鑑み、審決において、本件出願クレームを101条で拒絶した理由を全く解せないわけではないが、本件はまさに米国特許における重要な課題である。AI関連の革新的な発明を除外するということは、米国にとって重要な新興技術におけるリーダーシップを損ねることになる。
しかし、審判部の判断に従えば、多くのAI関連の発明は、明細書に十分に記載され、非自明であったとしても、特許を受けられない可能性がある。というのも、審判部は実質的に、あらゆる機械学習を特許不適格な「アルゴリズム」と同一視し、残る追加要素を「汎用的なコンピュータ構成要素」として扱い、その理由付けも十分ではなかったからである。審査官や審判部は、このようにクレームを過度に一般化して評価するべきではない。
しかしながら、特に問題となるのは、本件において審判部が職権で(sua sponte)行ったこの判断である。それは Enfish 判決の明確な判示を無視し、確立された判例を顧みず、表面的な分析だけで置き換えてしまったからである。審判部は特に職権による判断を行う際には、より慎重に扱うべきである。
同時に、本件クレームは103条(進歩性)に基づいても拒絶されている。本件は、102条、103条、112条が、特許保護の範囲を適正に決定するための伝統的かつ適切な手段であることを示している。審査は、これらの法定要件に焦点を置くべきである。
クレーム1はAbstract Ideaを規定しているかもしれない、しかしクレーム1はAbstract Ideaを権利化しようとするものではない。クレームの他の構成要素によってクレーム全体としてAbstract Ideaを現実的な適用に統合している。この判断は他の独立クレーム18と19、及び、従属クレーム2-6, 8-17, 20にも適用される。
結論:
審決の新規101条拒絶のみ破棄する。
--------------------------------------------------------
※ 本件の上訴審判パネル(Appeals Review Panel):
Squires長官(Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and USPTO
Director)を議長とし、Valencia Martin Wallace特許庁次長(Acting Commissioner for Patents)およびMichael
W. Kim副主席特許判事(Vice Chief Administrative Patent Judge)の3名で構成される上訴審判パネル
※
Mayo v. Prometheus 566 U.S. 66(2012)
Alice Corp. v. CLS Bank Int’l 573 U.S. 208(2014)
※
Enfish, LLC v. Microsoft Corp.,
822 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■